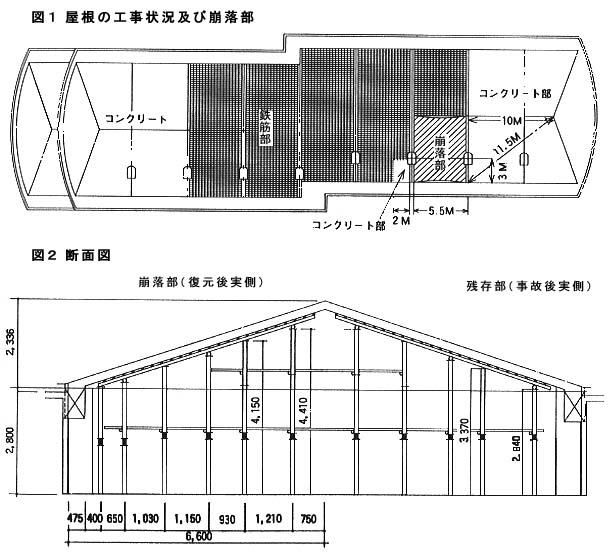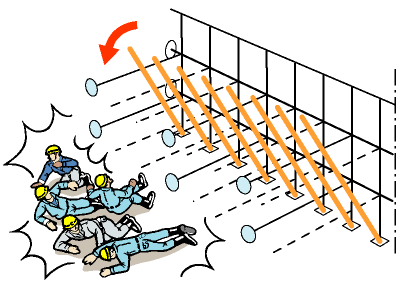
発生状況
この災害は、地上5階建て、鉄筋コンクリート造建物の建設工事において5階のB工区で、コンクリート打設中に発生したものである。
当日は、5階B工区のコンクリート打設作業を計画していた。コンクリート打設作業は午前8時30分から開始され、コンクリート圧送車を2台使用し、2ヶ所に分けて実施されていた。
午前中、B工区の約1/4のコンクリート打設作業を行い、計画通りに終了した。昼の休憩後、12時30分頃から残りのコンクリート打設作業を開始した。災害は、4本の柱と大梁に囲まれたスパンの内(B工区中の一部)で発生したものでその部分は、小梁を境にして階高が異なっていた。また小梁の片側は、午前中に施工した部分と同様の階高であったが、小梁の反対側は、下階(4階部分)が車路スロープとなっており、階高が他の部分よりも高くなっていた。
午後1時頃、小梁を境に階高が低い側のコンクリート打設を行った後、階高が高い残り部分のコンクリートを打設していたところ、突然小梁の箇所が陥没し、打設部分のスラブが抜け落ちた。
その結果、当該部位のスラブ上で打設作業に従事していた作業員6名全員が、階下の4階及び車路スロープ部まで型枠部材と共に墜落し、被災した。
原因
この災害の直接的な原因は、型枠支保工として用いたパイプサポートの座屈によるものと考えられる。
労働安全衛生規則第242条には、「パイプサポートを支柱として用いるものにあっては高さが3.5mを超えるときには、高さ2m以内毎に水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。」と規定されている。
この災害においても、支保工の横変位を防止するための水平材は、上記の様に設けられていた。しかしながら、小梁と平行な方向の水平材は、壁まで達しており、その方向については拘束されていたと考えられるが、小梁に直交する方向の水平材は、壁まで達しておらず、支保工の横変位防止に寄与できていない状態であったと考えられる。さらに、この水平材は、全ての支保工に取り付けられるべきであったにもかかわらず、支保工の数本毎に配置されていた。
そのために支保工が、座屈を起こし、その支保工で支えられていた小梁が、落下したものと考えられる。
対策
建設現場における作業効率促進のため、施工方法の標準化は、各施工業者毎に作製されており、施工性及び安全性の向上について、成果が上げられている。今回の災害は、この様な、標準化を過信した結果起きた災害であると言える。
同種災害の再発防止のためには、次のような問題を繰り返さないことが重要である。
1 施工計画の整備
この災害が、発生した部分は、標準組立図では対応できない部分であったにもかかわらず、標準組立図で対応してしまい、安全性の確認を怠った。
2 施工の実施
支保工は、45cm間隔で組み立てられるべきところ、90cm間隔で組み立てられていた。また、支保工の横変位を防止するための水平材は、直角2方向に堅固な壁に達するように、に設けらる必要があるが1方向の水平材は、壁まで達しておらず、支保工の横変位防止に寄与できていない状態であった。さらに、水平材の数もサポート数本ごとにしか設置されていなかった。この様に、組立図に合致した施工が、正確に行われていなかった。
3 施工管理体制の不備
前記したように、支保工の施工に不備があったにもかかわらず、形式的に点検されているだけで、支保工の間隔、水平つなぎの不備について、確認していなかった。