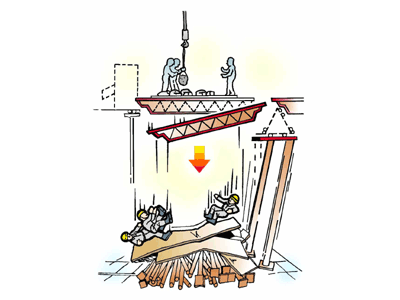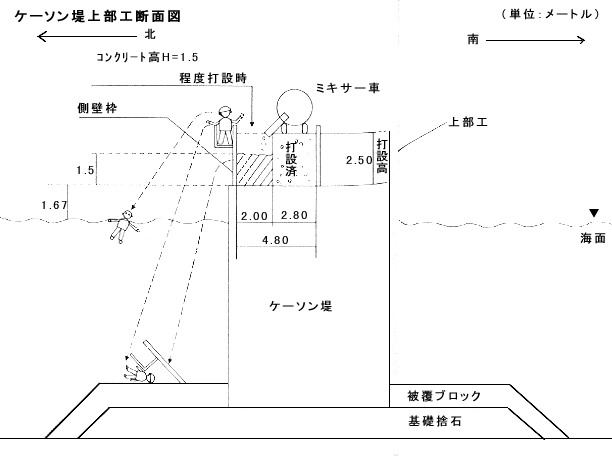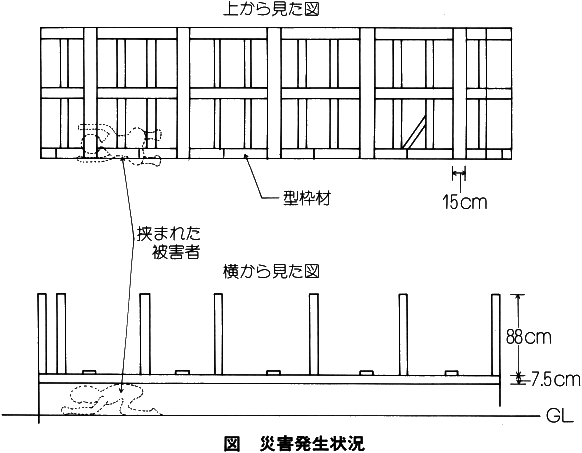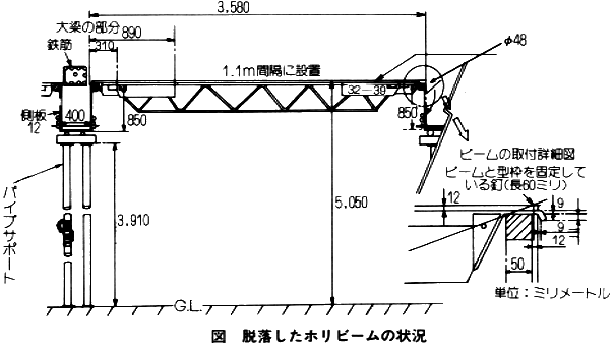
発生状況
本災害は、鉄骨・鉄筋コンクリート造ビル建築工事において、梁受けビーム式型枠支保工を組み立てた後、張り筋、スラブ配筋に使用する鉄筋を図に示したように型枠上に搬入し、その後、圧接溶接抜取り調査のため元請企業の作業者等3名が検査のため、型枠上に上がり検査を実施したが、検査の後片付け中に型枠が倒壊したため、3名が墜落負傷したものである。
本工事は民間発注の工事であり、倒壊した型枠支保工は災害発生の4日ぐらい前に他の下請業者によって組み立てられており、その際の型枠支保工の組み立て等作業主任者等の資格については問題ない。
型枠支保工の構成は図に示したように、ビームは約1.1m間隔に設置し、梁受けビーム式の型枠支保工で梁の間隔は3.6m(サイドビームを両端に19cm出した状態)、梁下の支保工部(パイプサポート部)はダブルのサポートで、その高さは3.9mであり2mの高さに水平つなぎを取っている。なお、倒壊した「梁」はリース品でメインビーム、サイドビーム、セット楔によって構成されている。また、梁型枠側板部は高さ80cm、厚さ12mmの合板に45~50cm間隔に縦桟木(幅4cm、厚さ4cm)を側板部内側に入れて補強の措置がとられていたが、側板の上部と中間部のセパレータおよび横繋ぎは梁鉄筋が配筋されていたにもかかわらず取り付けられていなかった。型枠パネルとして使用していた型枠用合板および桟木については、桟木に節部分が1カ所認められた他は、腐食等の欠陥部分は認められなかった。
なお、支保工に用いたパイプサポートの強度およびその構造については、型枠支保工用のパイプサポート等の構造規格に合致していた。
本建設現場における作業の指示については、月に1回「安全衛生協議会」を開催しておりその中で、おおよその工程の流れを説明するとともに、毎日午後3時ごろには1次下請けを集め、「安全工程打合せ」を翌日に行う作業の内容についての指示を含め行っている。1次下請けは打合せ会の後、関係労働者に対して関係事項につき指示を行っているが、本件も含め鉄筋の配置については、今までも特に指示はなされておらず、鉄筋工事を担当する下請け事業者の判断に任されていたものである。
原因
| [1] 強度が不十分な梁用型枠を「作業構台」の替わりにし、型枠上に重量物を積載したこと。 [2] 梁枠を支えていた型枠の添木が内側に取れていることから、梁の型枠が内側に押され、爪の部分が離脱したと考えられることから、次のことが要因と思われる。 | |
| [イ] 鉄筋の敷き方がスラブのビームに対して垂直でないため、荷重が平均化せず偏荷重になったこと。 [ロ] 縦桟木の真上にビームがなかったと仮定すると、梁枠の高さが85cmと高いため、厚さ12mmの側板では強度が十分でなく、折れ曲がる(折れる)可能性のあること。 [ハ] 梁枠側板の上部と中間部のセパレータおよび横繋ぎが取り付けられていなかったため、側板の折れ曲がる(折れる)原因の一つになったこと。 | |
対策
[1] 基本的には、梁用型枠を作業構台として用いないこと。仕方なく用いる場合には、梁枠の強度等を確認し、その強度の範囲内で作業の進行状況に合わせて計画的に積載すること。
[2] 施工計画に添って作業手順書等を整備し、梁型枠への積載荷重を含め具体的に下請けに指示すること。