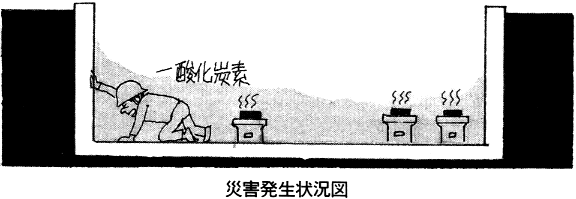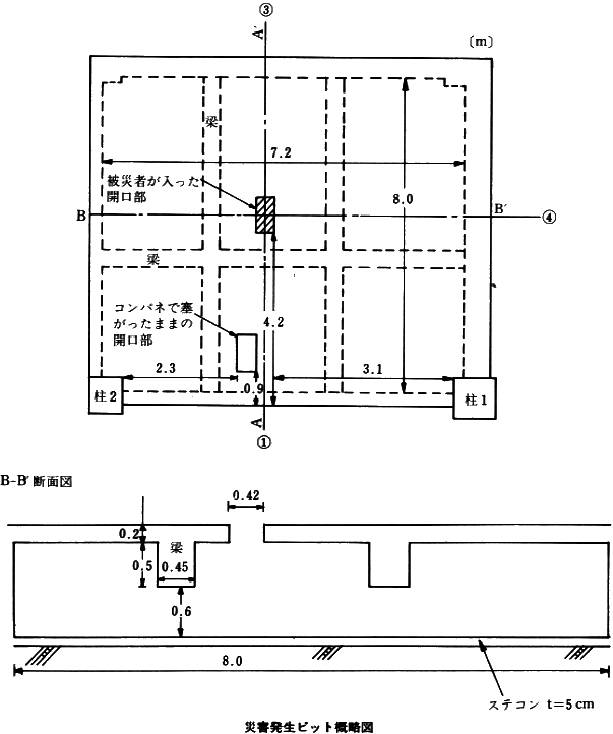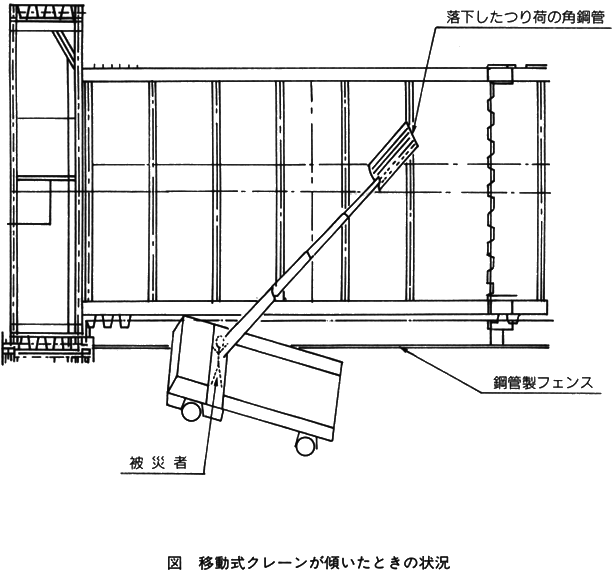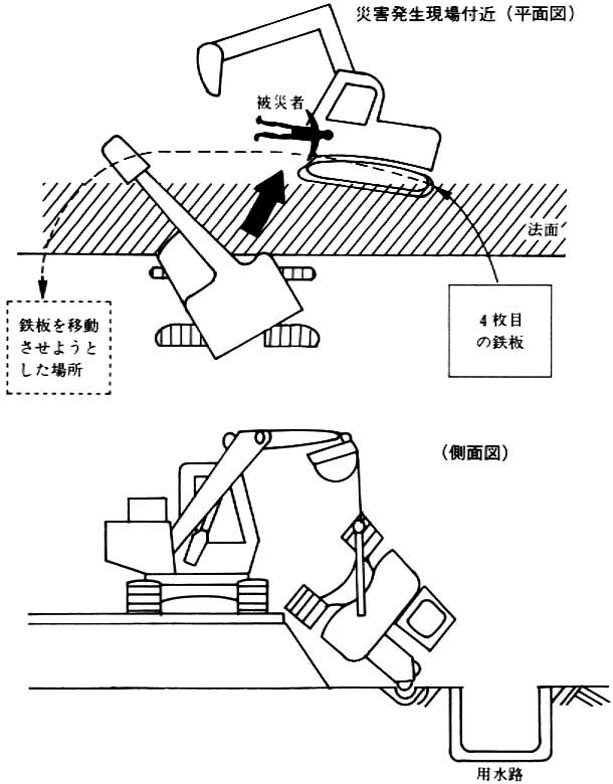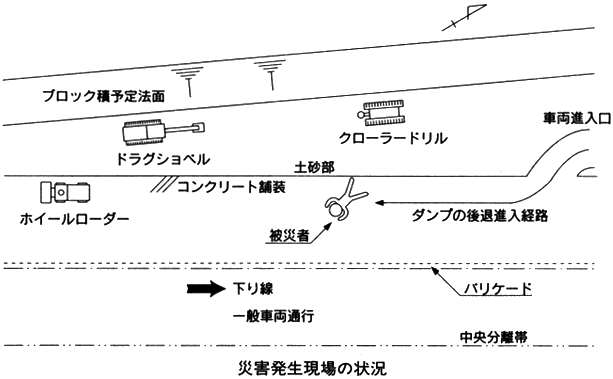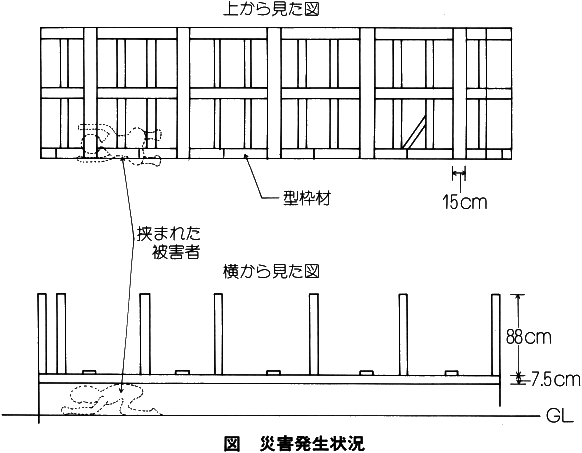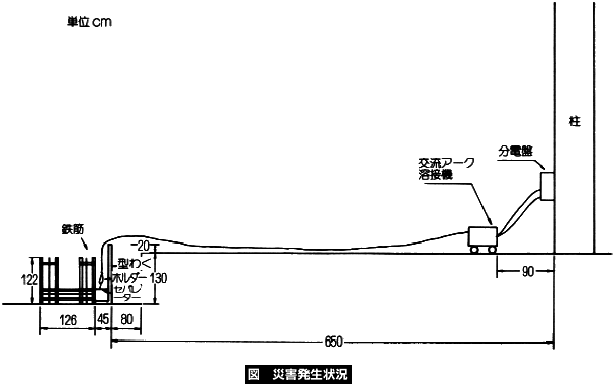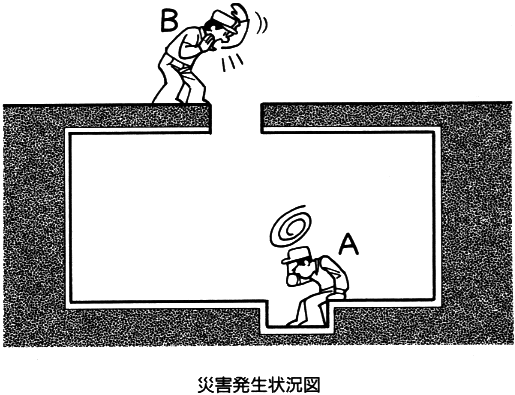
発生状況
本災害は、建築工場現場の地下ピット内の型枠解体作業を行うため、溜まっていた水をポンプで汲み出しながら作業の準備をしていたところ、ピット内の酸欠空気により被災したものであり、これを救助しようとした事業主も被災したものである。
災害発生当日、被災者Aと事業主Bはピットの型枠解体作業にとりかかるためピットの蓋を開けたところ、ピット内に水が溜まっていたので揚水ポンプにより水を汲み出していた。
10分程経過した後、ピット内部に溜まっていた水が減ってきたため、Aは型枠解体作業を開始しようとピットの口にはしごをかけてピット内に降りた。このとき、Bは地上にいて、作業に必要な工具などの準備をしていた。
Bがピットの中を見ると、Aはピットの底の溝になっている部分に腰を掛けた状態で動けなくなっていた。Bは地上からAにピットから上がるように指示したが、自力で上がることができそうもなかったため、救出しようとピット内に降りたところ、同様に被災した。
災害の発生したピットは、コンクリート打設養生のため、梅雨の季節に約2カ月間放置され、雨水が滞留しており、好気性菌による酸素欠乏状態であったと推測される。
原因
本災害は、作業を行う者に当該ピット内部分が酸素欠乏危険場所であるという認識がなかったことが、災害の発生を招いたと考えられる。そのため、作業を開始する際に、作業の危険性について関係者間での十分な連絡調整を図ることが重要である。関係者に酸素欠乏の発生の原因や発生しやすい場所及びその危険性等の知識があれば、酸素欠乏危険作業主任者の選任や酸素濃度の測定の実施などの対策が講じられ、災害の防止ができたものと考えられる。
対策
[1] 作業を開始する前に、当該場所の空気中の酸素濃度を測定すること。
[2] 当該場所の酸素濃度を18%以上に保つように換気を行うこと。
[3] 酸素欠乏危険作業主任者を選任し、所定の職務を行わせること。
[4] 作業従事者に対して、酸素欠乏症にかかる特別教育を行うこと。
[5] 緊急時の対応として、呼吸用保護具を使用すること。