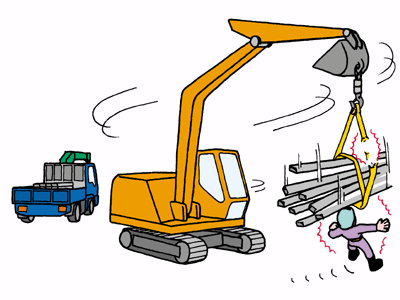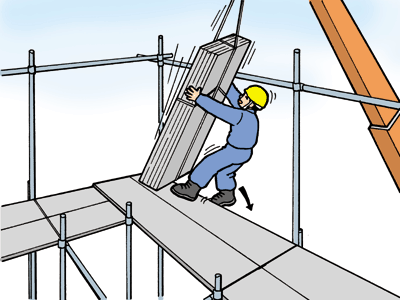
発生状況
この災害は、国道新設工事のうち橋台の建造作業中に発生したものである。
この工事は、2つの橋台と1つの橋脚で構成される橋梁を建設するものであるが、災害は橋台の型枠組立に付随する型枠の荷上げ作業中に発生した。
前日までに橋台の型枠7段目までのコンクリート打設が終了しており、災害発生当日は、被災者の会社から世話役を含め9人の作業員、それにオペレーター付の移動式クレーン(25t)で朝から型枠の組立作業が行われ、午前中には8段目と9段目の鉄筋組立てと型枠の取付けが終了した。
午後は、最後の10段目の型枠取り付け作業を行うことになり、被災者は地上で型枠の束の玉掛けをして足場に昇り、移動式クレーンの運転士に合図をして荷の取込み、玉外しを行っていたが、型枠6枚を束にして吊り上げたところ、風で荷振れしたので、再度地上に降り、6枚束を2組にして玉掛けをしたのち足場(高さ約13m)に昇り、合図して吊り上げたところ、型枠で被災者の姿が運転士の視界から一瞬消えたときに、足場上から転落し、肺挫傷、大腿骨骨折などにより同日中に死亡した。
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
| 1 | 風が強い中で作業を強行したこと 午後の作業を開始したときには、山間部でもあり、かなりの風が吹いていたので移動式クレーン運転士が「無理だから止めよう」と再三言ったのに、被災者が「大丈夫」と言って、荷振れを止めるため型枠を倍にして吊り上げさせるなど作業を強行したことが原因の一つである。なお、現場付近の風速は、4~5m/秒と推定される。 |
| 2 | 墜落防止措置が不十分なまま荷の取り込み作業を行ったこと 墜落直前の被災者の動作の目撃者はいないが、被災者の立っていた足場には92cmの高さにパイプ手すりが取付けられていたので、通常の状態では墜落することが考えられないので、足場の高さに来た型枠を手で取り込もうとしたときに、手すりを乗り越えたか、手すりと足場の作業床との間から墜落したものと推定される。 なお、被災者は、命綱は着帯していたが、使用はしていなかった。 |
| 3 | 安全管理を行っていなかったこと 朝のミーティングで現場責任者から「風が強いから気をつけるように」との注意があったが、作業が開始されてからのち、現場の状況を見ながら適切な指示などは行われていなかった。 また、被災者は、大工職であり、玉掛けの資格者ではないのに、玉掛け・玉外しの作業を行わせるなど安全管理を行っていなかった。 |
対策
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要と考えられる。
| 1 | 風の強いときには荷上げ作業を行わないこと 10分間の平均風速が10mを超える場合には移動式クレーンによる作業は禁じられている(クレーン則第74条の3)が、それ以下の風速であっても荷振れ等を増幅するおそれがあるので、現場責任者はその時々の状況を判断し、作業の中止などを命ずることが必要である。 |
| 2 | 無資格者に玉掛け作業を行わせないこと 吊り上げ荷重が1t以上の移動式クレーン等の玉掛け作業は有資格者でなければできないことになっているので、そのような作業の場合には必ず有資格者を配置しなければならない。 |
| 3 | 墜落防止措置を講ずること 作業床と手すりとの間隔が90cmもあるときには、中間に中さんを取り付けること、又は命綱を取り付けて確実な墜落防止を行うことが必要である。 |
| 4 | 安全管理を徹底すること 現場責任者は、ミーティング等において抽象的な注意を行うだけではなく、具体的に指示をするとともに、作業状況をチェックし、作業中止などの適切な指示を行うことが必要である。 また、あらかじめ、作業に必要な人員、資格者の配置を行うとともに、作業方法・手順を明確に定め指示することが必要である。 |