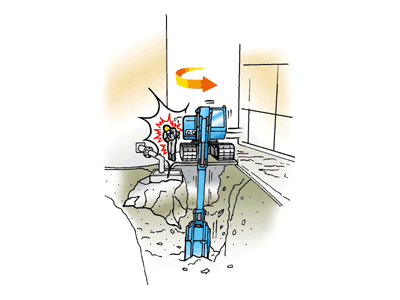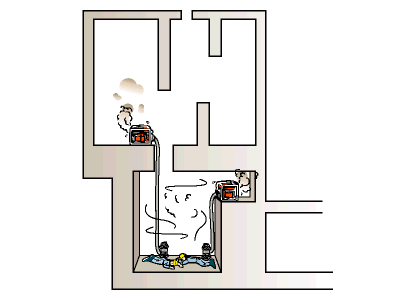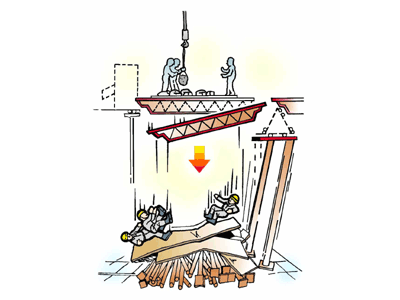
発生状況
この災害は、鉄筋コンクリ-ト造の事務所新築工事現場において型枠が倒壊し、作業員3名が被災したものである。
当日、この工事現場では、2階床の型枠建て込み作業、1階の型枠解体作業、2階への鉄筋荷上げ作業、2 階の配筋作業等が行われており、現場には元請の職員6名と、一次下請および二次下請から鉄筋工等23名の作業員が入場していた。
朝の打合せ後作業が開始され、被災者達は、まず2階の床に配筋するための鉄筋約20トンを現場に設置されたタワ-クレ-ンを用いて、トラックから2階床に上げる作業にとりかかった。
まず、トラックで搬入された鉄筋のうち約4 トン分を2階床の型枠上の何か所かに分けて荷上げし、次いで約4 トンの鉄筋を2階中央部分の何か所かに分けて荷降ろしを行った。
続いて、トラックに残っていた約2 トンの鉄筋を型枠の中央部分に降ろそうとしたところ、突然中央部分の2階床の型枠が倒壊した。
このため、荷外しをしていた3名のうち2名が鉄筋および型枠材とともに1階スラブ上に落ち、また、1階で型枠の解体作業の打ち合わせをしていたとび工の2名のうち1名が落ちてきた鉄筋、型枠材などに当たり負傷した。
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 型枠支保工の組立てが終了していないのに重量物を仮置きしたこと
2 関係作業者同士の連絡を十分に行なわずに作業を進めていたこと
対策
この災害は、鉄筋コンクリ-ト造の事務所新築工事現場において型枠が倒壊し、作業員3名が被災したものであるが、その対策としては次のことが考えられる。
1 鉄筋等の重量物を仮置きするときには、型枠支保工等の強度を確認すること
2 関係作業間の連絡調整を十分に行ったうえで、作業を開始すること
3 ノンサポ-ト工法についての検討と安全教育を実施すること