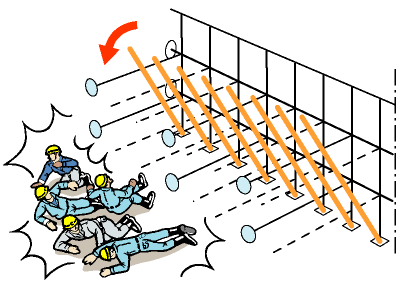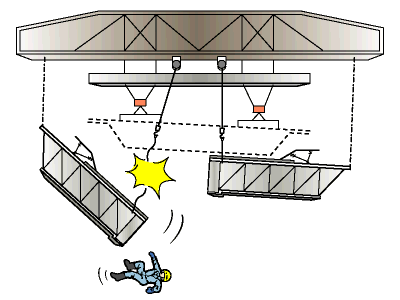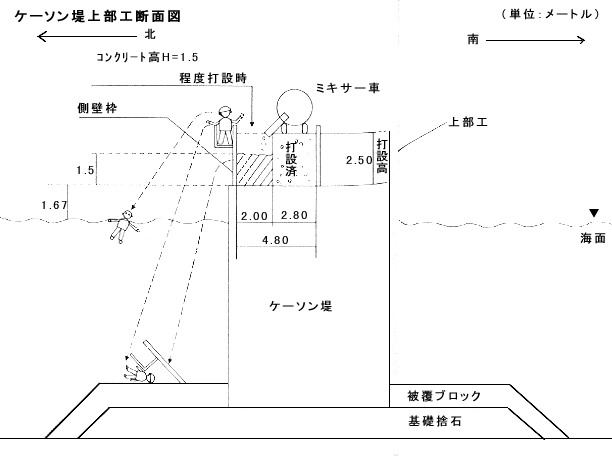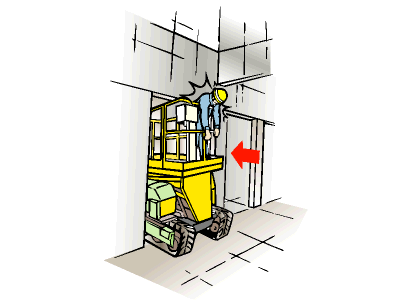
発生状況
この災害は、6階建の工事現場の地下室において、コンクリート壁の仕上げのため、高所作業車に乗り移動中の被災者が、扉取付部の下がり壁と高所作業車の手すりとの間に挟まれたものである。
当日の作業は、コンクリート打設後の壁面に残った型枠材接続用金具の跡をモルタルで埋めて仕上げる「Pコン埋め」と呼ばれる作業であった。
作業は、職長と被災者及び同僚の3名の合計5名で行われ、職長と被災者はそれぞれが単独で高所作業車を運転して高所作業車上で作業を行い、他の2名は一組となって高所作業車上の作業及び高所作業車の下での作業、他の1名は単独で足場上で作業を行っていた。
当日は、午前8時30分頃から地下での作業を開始したが、職長は職長会に出席するため途中で作業場所を離れ、他の4名は昼食時間をはさんで午後1時30分頃から午前と同じ分担で作業を開始していた。
職長は、午後2時頃に作業場所に戻ったが、このとき、被災者と高所作業車1台が作業場所にいないことに気がついた。
午後2時45分頃、被災者が、地下1階の下がり壁と高所作業車の手すりとの間にはさまれているのを他の会社の作業者が発見した。
被災者は、直ちに近くの病院に運ばれたが、同日の午後3時30分に死亡した。
原因
この災害の原因としては次のことが考えられる。
1 被災者は、高所作業車(作業床高さが10m未満)の運転について特別教育を受けていないため、高所作業車の運転に対する知識、技能が十分でなかったこと
2 高所作業車を用いて行う作業に関する作業計画が定められていなかったこと
また、高所作業車を用いて行う作業の指揮者も定められていなかったこと
3 通り抜けようとした扉取付用開口部の寸法に対して、使用していた高所作業車の余裕がなかったこと
対策
この災害は、6階建の工事現場の地下室において、コンクリート壁の仕上げのため、高所作業車に乗り移動中、扉取付部の下がり壁と高所作業車の手すりとの間に挟まれたものであるが、同種災害を防止するためには次のような対策の徹底が必要である。
1 高所作業車の運転の業務には、技能講習または特別教育を修了した者の中から、事業者が指名した者を就かせること。
また、指名された者以外の者が運転することのないよう、「キー」の保管を確実に行うこと。
2 高所作業車を用いて作業を行うときは、あらかじめ、作業場所に適応する作業計画を定めること。
3 作業開始前に作業の場所、手順、分担、安全上配慮すべき事項等について十分な説明、打合せを行うこと。
また、指揮者を定めて作業を行うこと。4運転者について、技能向上のための教育を実施すること。