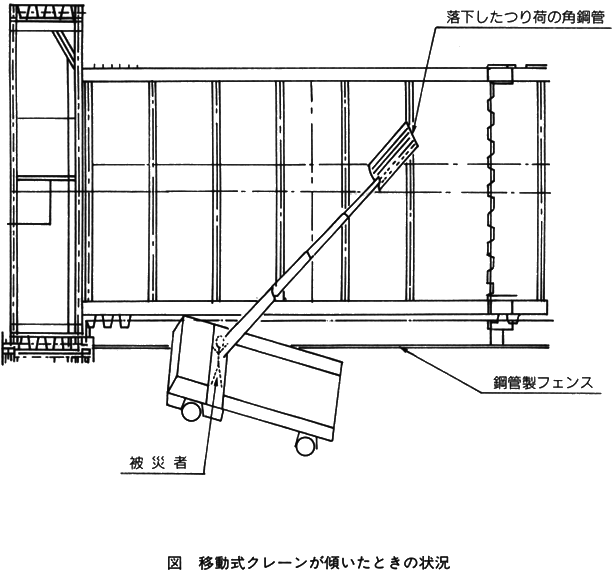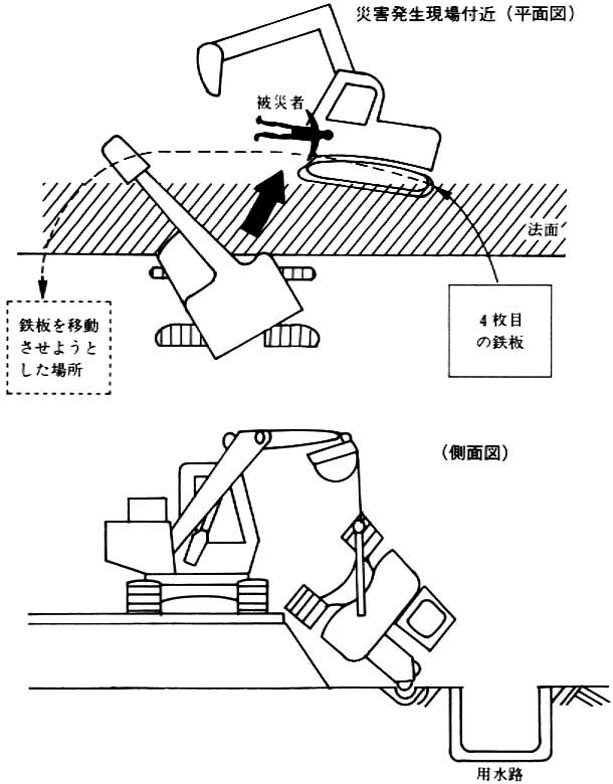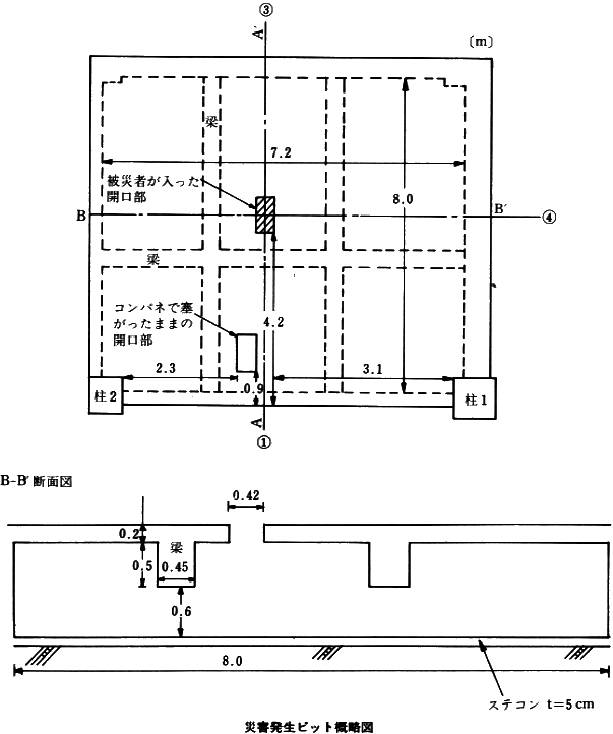
発生状況
本災害は、工場新築工事において、既にコンクリートを打設し終わったトイレ用配管ピットの型枠解体作業において、作業者が型枠解体のためピット内に立ち入ったところ、酸素欠乏症により倒れたものである。
災害発生当日、午前8時からの全体朝礼の後、職長Aが、当日の作業として1階女子トイレの配管ピットの型枠解体作業を行う旨を説明した。
引き続いて、作業開始。まず、ピット内の様子を確認するため作業者Bがピット内に入ったが、変わった臭気を感じたのですぐ息を止めて外へ出た。
そこで、Bは元請の作業者Cを呼び、送風機を持って来るよう依頼したが、それによる換気を待たず再びピット内に入った。そして、やはり臭気を感じ、急いで息を止めて、かろうじて外へ出た。その後、しばらく休息していたものの、次第に頭痛、吐き気がひどくなり、救急車で病院に運ばれ診断を受けたところ、酸素欠乏症と診断され、30日程度の休業を要するに至った。
災害発生後、現場を調査したところ、ピット内は湿度が非常に高く、カビ臭があり、床、壁等には水滴が付着していた。また、型枠はかなりの湿気を含んでおり、随所で腐食し、菌類が発生していた。硫化水素濃度は、酸欠則に規定する10ppmを超えていなかったが、酸素濃度は16%程度であった。
これらのことから、ピット内に酸素欠乏空気が発生した原因は、コンクリートの打設以来ほとんど密閉された状態が4カ月ほど続いており、また季節が夏ということで、連日の暑さにより、しみ込んだ雨水などに含まれる有機物が腐敗したり、菌類が発生したりすることにより、酸素が消費されたためと考えられる。
なお、本災害が発生したピット内部は、労働安全衛生法施行令別表第6の第3号「ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きょ、マンホール又はピットの内部」に該当し、事業者が同場所における作業を行うにあたっては、酸欠災害防止のため、酸素欠乏症等防止規則に規定する所要の措置を講じなければならない。
原因
[1] 雨水等がピット内にしみ込み、内部で微生物、菌類などが繁殖し、酸素が欠乏したこと。
[2] 事業者に、災害が発生したピット内部が酸素欠乏危険場所であるとの認識がなかったこと。
[3] 作業を開始する前に、ピット内部の酸素濃度の測定を行わず、酸素濃度が18%以下になっていることを確認しなかったこと。
[4] ピット内部を換気せず、作業者に空気呼吸器等を使用させなかったこと。
対策
[1] 酸素欠乏危険作業を行う場合には、測定器具を備え付け、作業を開始する前にピット内の酸素濃度および硫化水素濃度を測定すること。
[2] 上記の測定結果をもとに、作業場の空気中の酸素濃度を常時18%以上に、かつ硫化水素濃度を10ppm以下に保つように必要な換気を行うこと。
[3] 作業の性質上換気することが著しく困難な場合には、空気呼吸器等を備え付け、これを作業者に使用させること。
[4] 第2種酸素欠乏危険作業主任者を選任し、その指揮のもとに作業者に作業を行わせること。
[5] 酸欠作業に就かせる作業者に対し、酸素欠乏の発生の原因、酸素欠乏症を防止するための対策等について、特別の教育を行うこと。